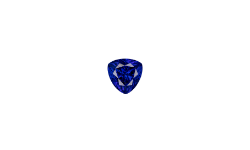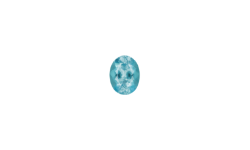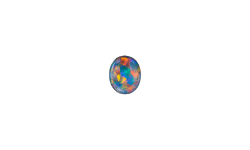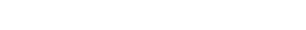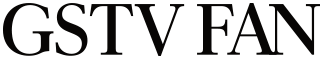新連載「モチーフから見る宝石彫刻」を2月からスタートしました。第1回目は、宝石彫刻の起源の時代(紀元前4000年~紀元前1000年頃)のモチーフについてお話ししました。第2回目は、紀元前4世紀~紀元前1世紀頃のヘレニズム時代にフォーカスしてご説明します。
(番組ガイド誌「GSTV FAN」2023年4月号掲載記事をWEB用に再編集しております)
ヘレニズムとは
ヘレニズムとは、古代ギリシャ人が英雄ヘレンの子孫という意味の「ヘレネス」と自らを呼び、その土地を「ヘラス」と言ったことに由来し、「ギリシャ風の文化」を意味しています。
紀元前4世紀、アレクサンダー大王(アレクサンドロス3世)の東方遠征によって、ギリシャ文化が中央アジアまで広がっていき、ギリシャ文化とオリエント文化が融合されたヘレニズムと呼ばれる新たな文化がもたらされました。ヘレニズム文化です。
一方、時代を示すヘレニズムとは、アレクサンダー大王が亡くなった紀元前323年から、古代ローマによってプトレマイオス朝エジプト王国が滅亡した紀元前30年までの約300年間を指します。文化と時代区分を明確に分ける場合は、前者をヘレニズム文化、後者をヘレニズム時代と呼び分けることもあります。
この時代、ギリシャ世界はかつてないほどに拡大し、活発な交易・経済活動によって一般市民の生活も豊かになっていきます。
美術品は王侯貴族だけのものでなく裕福な市民層の間でも所有されるようになり、裕福な市民は宮廷をまねた装飾を自らの家に作るほどでしたミロのヴィーナス、サモトラケのニケ、ラオコーン像など写実的でありながら人間美や精神性が追求された素晴らしい大理石彫刻も、この時代に数多く作られました。
余談ですが、私自身パリのルーブル美術館を訪れるたびにミロのヴィーナスを鑑賞していますが、いつも人だかりができていて、注目度の高さを感じます。ヘレニズム時代は、ギリシャ美術の発展の最も豊かな時代の1つで、西アジアから北アフリカ、ペルシャ、エジプト、ヨーロッパへとその文化は広がりました。

前130年-前100年頃、ルーブル美術館所蔵
(筆者撮影)
ヘレニズム時代(紀元前323年~紀元前30年頃)のモチーフ
カメオ彫刻家であり宝石彫刻研究の第一人者であるゲルハルド・シュミット氏の著書『宝石に秘められた政治』によれば、これまで発見されているカメオの中で最古の作品は、紀元前150年から紀元前125年に作られた『蝶を追いかけるエロス』だと考えられています。黒海のタマン半島にある墓から出土した金の指輪にカメオがはめ込まれていました。タイトルからもわかる通り、このカメオはギリシャ神話に登場する愛を司る神がモチーフになっています。

約2.8×2.2 cm、3層縞メノウ。エルミタージュ美術館所蔵。
(提供:ゲルハルド・シュミット氏)
カメオ彫刻が始まったこの時代、宝石彫刻のモチーフは宗教的なもの、つまり神々や女神、神話などでした。もちろん、カメオだけでなくインタリオも数多く見られます。複数層からなる縞メノウはそれ自体が非常に美しく、彫刻によってさらに芸術性がプラスされました。ただし、当時は非常に小さいものしかなく、現代の私たちが手にするようなブローチ大のカメオはありませんでした。

約200mm×110mm。製作年:1977年。彫刻家:ハインツ・ポストラー氏。
(提供:ストーンカメオミュージアム)

紀元前300年頃。ウィーン美術史美術館所蔵。
(提供:ゲルハルド・シュミット氏)
ヘレニズムは、後の時代にも大きく影響を与えるほど芸術が深まり広まった時代です。まだまだカメオ彫刻は少ない時代ですが、ヘレニズムの影響を受けたと見られるカメオがこの後の時代に数多く登場することも興味深い事実です。

ヘレニズム期末頃。約3.0×2.7 cm。
ベルリン美術館所蔵後、現在紛失。
(提供:ゲルハルド・シュミット氏)
次回6月号では、カメオの黄金期である紀元1世紀以降にフォーカスしモチーフをご説明します。読者の皆さんもよくご存じの世界三大カメオも登場し、モチーフに大きな変化がもたされる時代に突入します。ご期待ください。