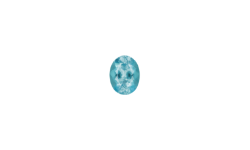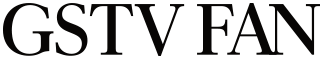要塞に四方を囲まれたこの街は、ポルトガル・オランダ・イギリスの支配を受けていたため、街のいたるところから様々な国の情緒を感じることができ、さすが奇跡の世界遺産と呼ばれる景観だった。
ガイドに案内された宝石店は元々病院だったところを改装してできたショッピングモールのような施設の中にあった。店主は親しげな笑みを浮かべ、私の要望と予算に見合った石を数点、店の奥から持って来てくれた。
―矢車草に近い色のサファイアがほしい
ノートにそう書かれていて、慌てて調べて保存した矢車草の画像と照らし合わせて一番近しい青色を選んだ結果、用意していたルピーはすべて使い果たしてしまったが、彼女の願いが叶えられたはずなので良しとしよう。加工は日本でする旨を伝えルースだけを受け取り店を出る。
「いいものが手に入ってよかったよ、それを使って日本でなにを作るんだい?」
ガイドからの問いかけに苦笑いをしながら答える。
「わからない」と。
彼女がこの石をどう身につけたかったのか、ノートに答えは書いていなかった。いつかの話の中で言っていたかもしれないが、生憎私の記憶をたどってもそれは思い出せない。
「まぁ折角の良い買い物だ、ゆっくり考えて良いモノを作ってくれ。この先の角に美味しいビリヤニの店がある。晩御飯はそこにしよう」
私はガイドの言葉に頷き、旧市街の中心地を目指した。